
多和田悟 共に生きる その1~決めるのは私~
ホーム 多和田悟トップ その2 その3
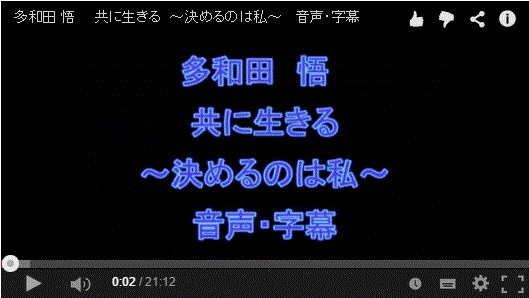 ■ ■ ■ 多和田悟 共に生きる ~決めるのは私~ テキスト版 ■ ■ ■ 盲導犬訓練センターっていいますと、最近では、テレビ結構出してくれるんです。新聞にも結構書いてくれるんです。 ですから、盲導犬が何をする犬かっていうのを、ほとんどの方に知って頂いていると思うんです。 ところが、実は何も伝わっていないということに、やっと気が付きました。盲導犬、目の見えない人の歩くことを手伝う。ここまではわかるんです。ところがどうも違いました。 僕、いろいろ意地をはって、信念を持ってやっておるんですけれども、果たしてこれは正しいのか正しくないのか。間違っておるのか間違っていないのか、また聞かせていただきたいなと思います。こういう仕事をしておりますと、どうも、違う事を考えてしまうんですね。僕、先程ご紹介頂きましたように、主にイギリスですけれども、イギリス、アメリカ、盲導犬の先進国と言われているところ、結構行くんです。行くんですけれども、大抵の場合「これはイギリスだから通用する話しで、逆に僕は日本で仕事しなきゃならん」こういう気になって帰ってきます。何か妙に日本風に構えて帰ってくるんです。「さあ、俺は日本に帰ってやるぞ」たんびそんな気分になるためにも、外国に出るってのは、いいことなんです。 外国行きますから、当然全て外国人なわけです。逆にいうと僕が外国人なんです。皆さん、意識されるでしょうかね。自分が外国に行ったら自分が外国人なんだっていうこと。で、外国行って感じますことは、まず、文化が違う、価値観が違う。ですから、僕の友人達、所長クラスの人達、全部「5時になって帰れないのは、お前に能力がないからだ」って言います。5時になったら、仕事なんであろうがスポーンと切って、さっと帰りますね。価値観が違うんです。彼ら仕事に人生を掛けるとか、そんな気はさらさらないみたいです。家庭のほうが大事、それはそうですね。僕みいにこうやって11日から娘の顔何日も見ていないっていうと、クレイジーで終わってしまいます。価値観が違うんです。 それと考え方が全く違うんです。日本で盲導犬が最初の頃、どう言われてきたか。「犬畜生に手ひかれて歩くくらいなら、家で寝とる」こういわれてました。さぞや昔の話しだろうと、江戸時代くらい昔の話かなと、そうじゃない、わずか10年ほど前の話しです、これ。外国いきましてまず、その人達の価値観が違う事にびっくりします。ですから向こうが大事にしてること、こちらが大事にしなければならない。 東本願寺、京都駅前にあります。あの前、古い町並みなんです。京都は間もなく建都1200年という記念すべき年を何年か先に迎えるわけです。あの回り、よく訓練で使うんです。っていうのは角が直角なんです、どこも。今の角はどれも45度切ってあるんです。で、狭くてしかも車は多くて、そして直角ですから、一歩前に出たらもう車にひかれるみたいなところがあるんです。そこ使うんですけど、そこ歩いてましたら、訓練ですから生徒さんがいます。この人がまた、僕より大きい人で、女の人で、髪の毛が本当にきれいな人で、美人なんですね。まあ、関係ないですが、、。その方歩いてましたら、おばあちゃん飛んできて、目の前に立ちふさがって、「あんた見えへんの、かわいそうになあ」って人が訓練 の時、前に立ちふさがるわけです。「あんたほんまに見えへんの」ってやるわけです。僕は指導員ですから、後ろで分からないようについて歩いてるわけです。たまに小道具もったりするんですね。新聞もったり週刊誌もったり。何か、見つかりそうになったりすると、本をひらいたりする。これは何でかっていうと、後ろに指導員が付いてるわかれば、周りの人、誰も助けてくれないんです。ですからちょっと隠れてやっておるんです。そうするとそのおばあちゃん、くどいんです。手のほうきとちりとりとポンとおいたまんま「あんた、ほんまに見えへんの」まだ聞いとるわけです。「可哀想になあ、若いのになあ」っておばあちゃん半分泣きそうになりながら。それ見たときに僕は、後ろから、おばあちゃん、まあまあって、そんな親切な気分はなかったですね。この~と思いました。もう後ろから行って何かしたくなるような、そんな気分になりました。ものすごくこう、空っぽの気分になっちゃったんです。で、考えてみてください。おばあちゃん、 涙ながして同情してるんです。かわいそうになあ、若いのになあ、ほんまに見えへんのってやってるわけです。そんな親切な、おばあさん相手に僕は後ろから行って、コーンてやりたくなりました。そうすると、場所によって、僕がそういう気分になったんですよって話をすると、何で?そんな親切なおばあさん、何で?って言われます。これを考える時に僕、いつも思い出すことがあるんです。僕は腹の中、むかむかしておったんですけれども、今日のテーマですけれども、共に生きるっていうテーマ。共に生きるっていうのは、実は何なのかな。一緒に肩組んで手つないで横断歩道渡してあげることかな。そしてそのおばあちゃんみたいに、涙ながらに同情することなのかな。いろいろ考えました。やはり、どれも違いました。共に生きる、、ここでいつも僕、考えてしまう。これは、その人が持つ痛み、その痛みを共にする事。もちろん喜びを共にすること大事です。ですけれども、その人がその障害のために、そのことのために痛みをもっているならば、その痛みを共に負うこと。これが、共に生きることだなっていうことに気が付きました。皆さんは日ごろ、ボランティアとして、いろいろ援助のいる方に対して、援助をしていただいているわけです。それは例えばボランティア、英語そのまま直訳しますと志願兵ですね。徴兵された兵隊さんじゃなくて、私が行きます、こういう人達、ボランティアなんですね。自分でやると決めた人達。皆さん、しなくてもいいんです、別に。家で普通の主婦をして普通にお母さんやってれば それでいいんです。世の中、時は過ぎていくんです。にも拘わらず、家にいてお母さんをやってたら、普通に、またお父さんをやっていたら、普通に、子供達にはそれ以上の時間が与えられるわけです。で、家庭としてもそれ以上の時間が与えられるわけです。ですけども皆さんは、あえてその時間を。その障害を持つ方の痛みを共にしようとされた。誰にやれと言われたわけではないです。皆さんが決めてやられている。日本の福祉を語る時に、どうしても慈善という言葉が日本の福祉の歴史にあることを覚えます。有り余る人が、ない人に分け与える、大事なことです。今の福祉は違います。福祉の理念は共に生きることです。一番大切なことは、自分がしてほしいようにすること。例えば、目のみえない人に、どういうふうに付き合ったらいいんでしょうかって、よく聞かれます。それが、あるお年の女性でしたら、自分の母親ならどうしてほしいか。子供の年であれば、自分の息子であればどうしてほしいか。そういう風に考えられたら、自然と決まってきませんかって、僕はお話しします。 盲導犬、最初、こう申しました。広く伝わってはおるけれども、間違って伝わっている、と、申し上げました。盲導犬を語る時に、ここを必ず押さえておきたいんです。お利口な犬が、目の見えない、何もできない、かわいそうな人を引っ張って歩いておる。この構図を作ったとしたら、その人はレストランに入る時、こう言わなければなりません。この犬はお利口です、暴れたりしません、静かにします、だから入れてください、こう言わなければなりません。僕は、間違ってもそんな事は言いません。盲導犬を定義する時に、目の見えない人が、犬の目を使って歩く。だから歩いているのは、目の見えない人、その人なんです。犬の目を使って歩いている。ですから、レストラン行っても、こう言います。私がお腹減りました。だから、レストランに入ります。犬が入るわけじゃないです。私が入ります。盲導犬が、お利口な、そして、目の見えない人が、何もできないっていうところに立ってしまったとしたら、共に生きる社会ってのは、ほど遠い社会になってしまいます。皆さんが今、目がみえなくなったら、ここから家に帰ることができません。そして大多数の人は、自分が今ここで 目が見えなくなったら、もう死ぬしかない、と思います。それはみなさんの自由です。自分が今、見えなくなったら生きていけないだろうと考えるのも、一つの方法です。ですけれども、間違っていけないのは、自分は、見えなくなったら死ぬしかないと思う、だからあの人達も、死ぬしかないと思っているんであろう、ってことは、思わないほうがいいです。 僕の仕事は結局何かって言われます。犬の訓練士でもなし、歩行指導員でもなし、何か。一番近いのはケースワーカーみたいな気がします。それはどんなケースワークをするかっていいますと、見えなくても、生きていけるんだよって事を伝える、こういう技術員なのかもしれません。去年の秋、NHKのラジオ視覚障碍者の皆様へっていう番組に出して頂きました。その時にアナウンサーのお姉さん、その中で彼女が一言目にこう言いました。「日本には今、何頭盲導犬がいるんですか?」って聞きました。台本にもそう書いてあったんです。「ちょっと待ってください。それおかしいです。その聞き方変」って言ったら、彼女「じゃあ、どう聞けばいいですか」って言うから「日本では、何人の視覚障碍者が自分の歩行補助具に、犬を選んでるか」こういう風に聞いてください。何頭の犬が、目の見えない可哀想な人を引っ張って歩いているかって聞き方しないでくださいって言いました。なぜなら、何頭の犬が、現在720と言われています。720頭の犬が720人の目の見えない可哀想な人を引っ張って歩いとる、これは避けておきたい。720人の人が、自分が歩く歩行補助手段として、犬を選択している。障害を受けるということ、どの障害に対しましても、そしてその障害の一番大きなところは何かっていいますと、自分が決める、自分が決めるということ、ここに制限を受けていることです。例えば、目が見えなくなったんだから、あなたは白い杖をついて盲学校へ行って立派な按摩さんになりなさい。自分が選んだ結果としてそうするっていうのは、障害を持たない人にもあることです。障害を持たない人は、むしろそうしてきています。ところが、あなたは目が見えないんだから、白い杖をついて盲学校へ行って、立派な按摩さんになる、自分の選択じゃないです。それ以外の選択を言おうもんなら、「お前は何をねぼけたことを言っておる。現実を見据えなさい」とこういう説教されるんでしょう、きっと。自分で選択することができなくなる。これ、大変なことなんです。それは、自分で選択をして自分で全て決めてやってる人達には、想像がつかないくらい、大変なことなんです。 日本点字図書館の本間和夫って方がいらっしゃいます。その、本間先生が若い頃、影響を受けた方の中に、熊谷鉄太郎って方がいらっしゃいます。この熊谷鉄太郎ってのは、日本で初めてキリスト教の牧師になった、盲牧師です。子の方が、こう言ってます。 本間和夫にこう言いました。「目の見えない人間が、どれほどの仕事を残せたか、これは、どれほど多くの人の目を使ったか、これに比例する」って言いました。この最初の、目の見えない人が、っていうのを、お前がに変えてみてもいいと思います。あなたがに変えてもいいと思います。あなたがどれほどの仕事を残せたか、これはあなたがどれほど多くの目、これを手に変えてもいいと思います。手を借りたか、知恵を借りたか、これによる、その量に比例する。我々にとって他人の知恵、手が、見えない人にとっては目になるわけです。生きていることがこれほど楽になった。我々は、時々間違えます。僕は頻繁に間違えます。自立って事を考える時に、独立独歩人の手を借りないでやることを、一つの 目標にします。それは場所によるんではないでしょうか。人の手を借りないでやるということ、僕はこれはまさに、主体をどこにおくか、ガイドヘルパーさんの側に、この歩行の主導権を渡してしまうのか、間違ってまた、財布を渡してしまってそのショッピングの主導権は誰がもつのか、主体の問題だと思います。ガイドヘルパーさん達は、その人の目になれます。しかし、それ、親切でやってらっしゃるお金のやり取り、本来、彼らがやるべき仕事。このことを引き受けて、交代してやることによって、彼の主体まで、もらってきていませんでしょうか。それはまさにお利口な犬が目の見えない可哀想な人の手を引っ張って歩いておる。言葉変えましょう。親切な時間を持ったガイドヘルパーさんが、可哀想な何もできない目の見えない人を引っ張って歩いてやっておる 。おんなじ図です。ガイヘルさん達が目指しておるのは、豊かな自分が貧しい見えない人達に慈善をするつもりはないはずです。家にいた人が、一緒に買い物にいくこと、このことを喜べる、ああ、あそこ行ってきたよね、一緒に行ったよね、そのことを喜べる、楽しい時を共にできる、そして駅前にある自転車、大変だよね、大変さを共有できる、そのことを喜びにして皆さんやってらっしゃると思います。報酬が目当てならば、スーパーのパートに行ってるほうが、よっぽどいい収入になる。そんな方はいらっしゃらないはずなんです。喜びを共にしたいから、そしてその人の持つ辛さ、これも一緒に担っていきたいから。これがボランティアさんたちの基本理念であるべきだと思います。一番大事なことは、主体なんです。盲導犬を触ってはいけないって言い方をよくされます。うちではそういう言い方は決してしないんです。仕事中の盲導犬触らないでくださいって言い方はしないんです。よその盲導犬協会の人達、盲導犬触らないでください、ここにいらっしゃるほとんどの人達、情報として盲導犬触っちゃいけないもんだと思っていらっしゃる。僕はそうは思わない。そういう人達に聞きました。何で触っちゃいかんのですか?協会が決めてますから。こんなんは論外です、理由として。続いて、訓練に気が散るから。三番目、訓練が壊れるから。こういう答えが一番多いです。僕はもう、反論、反論ですね。あなたは人が触ったくらいで壊れる犬に命預けてるんですか。あなたのところの協会は、人が触っただけで崩れるような訓練してあるんですか。そんなん、問題じゃないはずですよ。僕はどうも意図的に自分の意見を引っ張りだそうとするんです、いやらしいですね。じゃあ、どうですかって言われる。僕は、こう言います。触らせるか触らせないか、決めるのは私です。触らないでください、なぜか、私のだから。この犬を触っていいか触って困るかきめるのは私の仕事です。私が決めることです。触っていいか悪いか決めるのは、僕じゃないはずなんです。触られる側なんです。触られる側が決めることなんです。一番の大きな障害は、自らが決定すること、これを剥奪されること、と申し上げました。あなたは、目が見えなくなったんだから、白い杖をついて盲学校に行って立派な按摩さんになりなさい。このことと、今の事は主体論で、まったく一致するんです、僕にとっては。この、盲導犬を触らせるか触らせないか、このことに関して、こういう意見があります。「私の体の一部です。勝手に触らないでください」ってのがあるんです。身体論ですね。僕、身体論はおかしいなと思うんです。触らせるか触らせないか、決めるのは私なんです。それを決めるのが私なんです。このことはいやなんだ、このことはいいんだ、私は一人で行きたいんだ、一人で行きたくないんだ、決めるのは私なんです。● ● ● ● ● ● ページの一番上へ戻る |