
多和田悟 共に生きる その2 sympathy~痛みを共にする~
ホーム 多和田悟トップ その1 その3
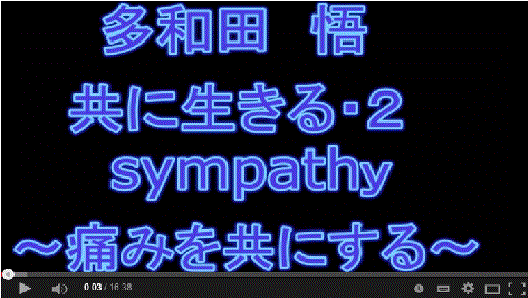 ■ ■ ■ 多和田悟 共に生きる sympathy~痛みを共にする~ テキスト版 ■ ■ ■ 京都で、千本北王子って所があります。ここの角には京都ライトハウスって所があるんです。視覚障碍者のリハビリテーションセンターです。この千本北王子、各4車線の大きな交差点です。ここで目の見えない人が、杖を突いて立ってました。中学生の息子を持つお母さんからの新聞の投書です。「うちの息子は意を決して手引きしましょうといった。そしたらその人はいらんと言った。うちの息子はもう二度と目の見えない人の手伝いなんかするもんかといっておる」こういう投書が載ったんです。また、別の話ですけども、アメリカから車いすで世界一周をしてる方がいて、その方、九州かどっかにいる時に、坂道があって、ついていった新聞記者かテレビの人か、何しろマスコミの人が、後ろから車いすを押した。そしたら彼は猛然と怒った。余計なことせんでくれって怒った。人の親切を何だと思ってるんだって、その新聞記者、書いてるんです。この、どちらも、先程僕が申し上げました主体論で考えてください。千本北大路の交 差点で、杖を持って立ってた人。そこへ行った中学生とそのお母さんは、こう決めました。「あの人は目が見えない。だから、困っているに違いない」こう決めました。ところが本人は、困っていないと言ったんです。私ここはいつもここ来てるから大丈夫。あなたの援助いらないって言ったんです。そしたらお母さんは、もう二度とうちの息子は声をかけることはしないだろう。と言った。そしてその車いすを押した新聞記者は、受けて側にも配慮がほしい、という言い方をしました。だけど僕は、主体論でいくと援助を受けるかどうか決めるのも当事者です。ですから聞くべきは、最初に「お手伝いしましょうか」これしかなかったはずなんです。で、その時に、その白杖の人はこういったそうです。「いらんわい」って言ったって。言われた中学生はがっかりしたでしょうね、確かに。でも彼にいらんわいと言わしたのは、それまでの歴史だったと思うんです。それともう一つは、教育って機会もなかったでしょう、彼に対しては。もう一つは、そこでもう一歩突っ込んで「お手伝いしましょうか」「いらんわい」って言われた時に「じゃあ、気を付けて」「大きなお世話だ」ってここまでは言わないですから、普通。車椅子の人に対してでもお手伝いしましょうか、お願いします、いいえ、結構です、自分でやりたいです。この、自分でやりたいってのは、特に中途失明で失明された方、わりとベースになってることです。自分でやりたい。買い物いきますね。買い物行きまして、僕、よく行くんですけれども、一緒に行って、僕は目ですから、カウンターのところまで行って、前に店員さんいらっしゃるよって言って、僕はちょっと離れるんです。これ下さい、これ下さい、ちょっと見せてください。やるわけです。その時に、おつりも手のひらにポンと渡された。私が買い物した。私の手におつりが返ってきた。何年振りかしらって、、。これは、当たり前のことだけに、当たり前になるという事は、非常に大事なことなんです。僕は先程から、リハビリテーションていう言葉、申し上げております。リハビリテーション、元に戻る。本来ある権利を回復する、ということです。この話、何回かした覚えがあるんで、聞かれた方もいらっしゃると思います。祗園祭りの時に、祗園ばやしを聞きに、四条通り行きました。あの通りの中、1キロ程の通りの中、20万人近い人がくるわけですから、もうラッシュの電車の中みたいなんです。テレビの取材が入ってました。そして、その中で、インタビュー受けちゃうんですね、やっぱ目立ちますわね、盲導犬連れてると。「毎年来られるんですか」「いいえ、この犬持ってから、また来るようになりました」「じゃあ、あなたはこの犬持たれて、人生変わったんですね」って、そのリポーターのお姉さん、ボロボロ泣いとるんです。僕、おっかしくてしょうがなかった。何を言ってんだろうな。そしたら彼がなんと答えたか。「見えてる時僕はずっと、毎年ここ来てたんです。見えなくなってこれなくなったんです。今、また犬を得てまた、これるようになったんです。元に戻っただけです。人生変わったわけじゃない、見えてたらみんなやってるんです」こう言いました。うちの訓練センターに年間2500人、およそお客様があります。去年は天皇、皇后両陛下来られたもんですから、ちょっと数が、3000人超えたと思います。その中で、見えない方が、約一割です。って言うと250人から300人です。その方々は、全員犬と歩いていかれます。そして犬ができること、わずかにしかないことを良く存じていらっしゃいます、覚えて行って頂きます。目の見えない人が、なぜ町を歩けないか、3つしかないんです、理由。簡単なんです。考えてみたらなんだ、と思います。角が分からない、段差が分からない、障害物が分からない。この3つだけです。角、段差、障害物、いつ出てくるか分かったら、見えなくても歩けます。犬はその情報を生でよこしてくるだけです。そしてその生で入ってきた犬が左を向いた、背中に付けたハーネスを通じて左を向いた、犬が伝えてきたのは、左を向いたという事実だけなんです。それを分析して、ひょっとしたら角があるのかな、何か右に障害物があるのかな、いろいろ分析をするのは本人なんです。角・段差・障害物これを分析して、クリアして歩いていく。そして、今私はどこにいて、どこを通って、どこに行こうとしているのか。このオリエンテーションの技術を使って、移動してるわけです。 見えにくい方、と、全く見えない方、この方々の違いは何かっていうと、見えにくい人達でも、見えておればいいじゃないか、見えなくなるまでの過程、として見えにくい方、ととらえたら、これ、間違えます。見えにくいという障害なんです。先日、2月に放送がありました、明日の福祉という番組で取り上げられた方ですけれども、見えにくい、奥さんが見えにくいんです。僕、これ、ラジオで一回、みにくいと言ってしまいましてね。「この人はちょっと、見にくいんで」後で顰蹙買いました。見えにくいと言えと。見えにくいんです。で、その人が、テレビの中でこう言いました。私、今までだって歩けてた。だけど犬使うと空が見えたんだよ。看板が見えたんだよ。人が見えたんだよ。今まで歩いてた時、しょうがないから歩いてた。犬連れてるとね、楽しいんです。って言われました。その人はご主人が全盲ですから、彼女は見える人なんです。ご主人にくらべると。僕に比べると圧倒的に見えない人なんだけれども、ご主人に比べると見える人。その次のクラスに、こられた方は、奥さんが晴眼なんです。で、ご主人は見えにくいんです。ですから奥さんに比べると見えない人なんです。ですから自分は見えない人できない人だったんです。その方、僕どうしても一生忘れられない出来事がありましてね。クラスに入りまして2日目、雨がザザ振りでした。四条の地下道へ行きました。一直線で一キロあるんです。地下道で。濡れないでエアコンきいてるし気分いいもんですから、そこ最初の導入で直線歩行でやるんです。半ばくらいまで来た時に、彼がいきなり立ち止まって「うおー」って声あげて泣き出したんです。「どうしたんですか?」って聞いたら、「一人で歩いてる」って言うんです。「あれ、今までだって歩いてたでしょ」「でも、昔と同じように歩いてるんだよ、昔こうやって歩いてた」そして、見える人の中に一人いますから、見えない人なんです。娯楽と言えば奥さんがパチンコ屋に連れていって、夕方、お昼に連れて帰る。 そんなような生活をしてるわけです。ですから一回負け始めると、2万円3万円と負けるような。で、僕こないだ冷やかしにいったんです。たまにはパチンコやってんですか。もったいなくてあんなところいけません。どこ行ってるんですか。川っぺり走ってます。っていわれた。 我々、バックグラウンド、コントラストによって、後ろの地によって、図が変わって見えるんです。見えない人の中にいる多少見えない人は、見える人なんです。見える人の中にいる見えにくい方は、見えない人なんです。四条の地下で、いきなりうおーって泣き出した彼は、空が見えた看板が見えたって言ったその奥さんよりも見えてるんです。ですから、我々がやろうとしていることは、技術の提供だけではなくて、生きていて良かった、楽しかった、このことをめざしているんだってことに気が付きました。皆さんはいろんな形で援助をされます。困ったかたを援助されます。困った方って言い方が僕わりと好きで使ってしまうんですけど、これはね、スウェーデンの友達に習ったんです。なぜかっていうと、スウェーデンで障碍者ってどういう風に定義してんのって僕聞いたら、公共交通機関に乗る時に、人の援助を受けたほうが使いやすい人。例えば年寄。降りるときちょっと手添えてもらったら、そういう人はみんな障碍者だ。だからスウェーデンには障碍者いっぱいいるよ、って言いました。そういう意味での障碍者の言葉の代わりに僕よく使います。 人の世話にならないこと、これが日本人の美徳でした。人に迷惑をかけないこと、これが美徳のようです。しかし、それは、熊谷鉄太郎のことば、本間和夫を変えた言葉。「視覚障碍者がどれほどの仕事ができたかは、その人がどれほど多くの人の目を使ったかによる」この言葉に励まされて本間和夫は勉強はじめました。これと同時に援助する側は、心をこめて同情しても、大きな溝を掘って反対側から「かわいそうになあ~」って大声で叫んで「大変だね~」って大声で叫んで、立ってる場所が違うんです。なぜか。私は可哀想でない人、あなたは可哀想な人。私は、援助する人、あなた、援助される人、可哀想になあ、、。共に、痛みを負担すべきところに立っていないんです。盲導犬を通じていろんなことを考えます。なぜ、われわれは盲導犬を提供するのか。それは彼らが歩くのが楽しかったよ、先程の弱視の奥さんが言われました。看板が見えてうれしかった。これ、テレビで言ってるんです。青空が見えてうれしかった。何年もみたことなかった。必死になって自分の足元見ていた。その人が変わったんです。歩くのが楽しいと言った。クオリティーオブライフって言葉があります。生活の質って言い方があります。僕はまさにクオリティーオブウォーキング、クオリティーオブライフ。これは例えば、お腹が満たされれば、お茶づけでもお腹は膨らむんです。一人暮らしで、ご飯にお茶かけて食べるだけでも、お腹は満たされるんです。腹を満たすことと食事することとは違いますでしょ。移動することと歩行することは、また違うんです。弱視の人、必死になったら移動ができたんです。でも、彼女は歩行してなかった。歩行ができるようになった。そのきっかけはわずかに犬です。皆さんが関わられる援助を求める多くの方が、その作業によって、楽しかったよと思えるところ。そこの部分に皆さんがいらっしゃるかどうか、これはかなり大きな部分で問われてくると思います。楽しかったよって言われる歩行。そして皆さんは、そのかかわりの中で、関わることの楽しさ、僕、英語で好きな言葉がもう一つあるんです。イッツ my プレジャー っていうんです。それは私の喜びなんだって言い方なんです。で、今日、おごってやるよ、おごってやるよって言うから、いいんだよ、俺だってたまには出したいよって言ったんです。そしたら違うよ、これ、イッツ my プレジャーていうんです。これは私の喜びだって言うんです。そして、夜の夜中に僕の忘れ物届けてくれて、おい、明日でもよかったのに悪かったねって言ったら、イッツ my プレジャー。果たしてこの言葉に変わる日本語はないんですけれども、皆さんが、必要とする人にかかわられる時に、その事が、イッツ my プレジャー、私も楽しかったよ、私もうれしかったよ、と言えた時に、まさに溝はそこになくなったと思います。皆さんは、私援助する人、あなた援助される人、私、可哀想でない人、あなた方可哀想な人、この関係では、共に、あるべき、痛みを負担すべきところに立っていないという事を覚えておいてください。そして、そのことを私の喜びと出来る、皆さんは、自分の時間を提供されます。そして、それを必要とする人と、痛みを持つ人、また、そのことで喜びを持つ人と同じ方向をむいて喜びをともにできる方々です。ともにある姿、同情という言葉で締め括らせて頂きます。同情というのは、英語でsympathy。この言葉の語源は、痛みを共にする、という事だそうです。このことはまさに共に生きるうえで、一番大事なことではないかなと思います。今日は、せっかく時間を頂きながら、盲導犬の話なんてのは、かけらも出来ませんでした。日頃ぼくが思っております関わり、そのことについてお話しをさせて頂きました。多分、皆さんと同じところに僕は立っておると思います。今日はどうもありがとうございました。(拍手)● ● ● ● ● ● ページの一番上へ戻る |